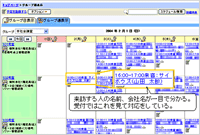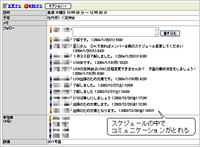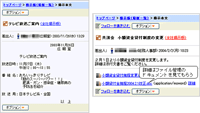導入製品 サイボウズ Office 6 | かんたんシリーズ
企業情報


■会社名:
月桂冠株式会社
■ホームページ:
月桂冠株式会社ホームページ![]()
■利用製品:
- サイボウズ Office 6 基本セット
- サイボウズ Office 6 ワークフロー
■利用人数:
360人
■業種:
製造業
■サーバー OS:
Windows 2000 Server
■管理者レベル:
兼任管理者
- 会社概要
- 導入前の状況 〜既存のグループウェアが利用されず
- 導入の決め手 〜無制限ならコストを抑えて全社員で利用
- 導入教育 〜パンフレットの挿絵でメリットを説明
- 導入効果 〜「サイボウズ Office」は情報のインフラ
- 活用方法 1「設備予約」 〜 利用のきっかけを作り、仕事が計画的に
- 活用方法 2「スケジュール」 〜予定を詳細に書いて、月報に利用
- 活用方法 3「掲示板」 〜関係する情報はその画面でやりとり
- 活用方法 4「アドレス帳」 〜PDAと同期を取って持ち歩く
- 活用の工夫 〜会議室予約だけは強制的に始める
- 今後の展望 〜「ワークフロー」を軸にポータル的な使い方を目指す
- システム概要
- 関連リンク
- ダウンロード
月桂冠株式会社
情報システム部情報システム第二課長 冨永 光則氏
情報システム部情報システム二課 辻村 寛之氏
まず設備予約をサイボウズに切り替えることで利用率をアップ。体裁だけの業務ならやめようという意識改善と業務改善に繋がった。情報インフラのベースとして活発に使われている清酒業界のリーディングカンパニーの利用方法に迫る!
たえず挑戦を続ける清酒業界のリーディングカンパニー
月桂冠は、長年、清酒業界のリーディングカンパニーであり続けている、知らぬ人のいない有名な清酒メーカーである。創業は江戸時代初期(1637年)なので、今年で 367年。まさに清酒業界の老舗だ。「老舗」というと伝統を重んじる古風な会社と思われがちだが、情報システム部情報システム第二課長 冨永 光則氏は次のように語る。
「実はチャレンジ精神にあふれた会社です。例えば、すでに明治 42年、防腐剤を入れない瓶詰め清酒を発売、樽詰が主流だった昭和 6年、本格的瓶詰プラントを導入したのも当社、1年を通して造る四季醸造システムも当社が初めて手がけたものです。同じやり方に固執するだけでは 300年以上も続かないと思いますよ」(冨永氏)
近年も「健をめざし、酒(しゅ)を科学して、快を創る」をコンセプトに、お酒の新しいライフスタイルを提案したことも話題になり、注目を浴びた。
導入前の状況 〜既存のグループウェアが利用されず
同社がグループウェアを最初に導入したのは 1998年だった。営業部門で各社員の横のつながりを強化するためのツールとして導入されたものだ。ただ、当時はサイボウズもできたばかりで知名度も低く、導入されたのは他社の製品だった。しかし、導入して 1〜2年で限界が見えてきた。
「ユーザーひとりごとにライセンス費用がかかるため、全社員分は用意しなかったのです。全社員で情報共有するには、追加コストの費用対効果がまるで検討もつかない状態でした」(冨永氏)
そのため、インターネット用のメールサーバーを別に用意して、全社員にメールアドレスを配布。社員間の連絡にはそちらを使っている状態だった。
また、運用、管理の手間も問題だった。パソコン 1台ごとにクライアントソフトのインストールや設定が必要で、仕様を変えるのも手がかかっていた。
「業務の変化に対応できず、不満の声が上がってきていました」(冨永氏)
そこで、今後その製品にさらにお金を投入して全社導入するか、別のグループウェアに乗り換えるかがの検討が始まったのである。

情報システム部情報システム第二課長 冨永 光則氏
導入の決め手 〜無制限ならコストを抑えて全社員で利用
検討を始めたころ、Web ベースのグループウェアが登場してきていた。Web ベースならクライアントのパソコンにはソフトをインストールする必要がない。Web ブラウザで操作できるので、操作も軽い。しかも携帯電話からも利用できる機能も持っていた。
それらの中で目を引いたのが「サイボウズ Office」だった。
「サイボウズ Office」は、クライアントパソコンの設定は不要で管理、運用が楽。しかも、ライセンス数無制限で購入すれば、何人で利用してもコストは変わらないので、社員数の大きな会社にとっては安心できる。
そこで「サイボウズ Office」について検討、2002 年1月に「サイボウズ Office 6」の前身である「サイボウズ Office 4」の導入をした。
「基本パッケージだけで機能が一通り揃っていますし、ライセンス数に無制限があるのが気に入りました。無制限を購入すれば、全社員にライセンスを配っても大丈夫。しかもリーズナブルな料金なので、たとえ全社で利用されなくても、必要な部署に浸透してくれたらそれだけでコストに見合うと考えたのです。
また、インターフェースが分かりやすいこともポイントでした。パソコンに詳しくない人にも、各機能の名前が、何をする機能なのかがすぐ伝わります。何をするためのものかがわかっていれば、操作もすぐに理解できます」(冨永氏)
導入教育 〜パンフレットの挿絵でメリットを説明
「サイボウズのパンフレットには、導入したらどういう効果があるか分かりやすい挿絵があり、何が実現できるのかがはっきりしていました。そこで『これがやりたいんでしょ』とメリットを訴えてから、基本的な操作方法を教えたのです」(冨永氏)
そうしてメリットを理解してもらってから簡単な講習会を行った。講習会で教えたのは、各部門のパソコンリーダー 30人ほど。彼らが自分の部署に戻って、各社員に伝授することとなった。
「講習会で教えたのは設備予約のやり方だけ。『サイボウズ Office』はすべての操作が同じ体系なので、ひとつの操作を覚えればすべての機能が使えますから」(冨永氏)
「サイボウズ Office」の利用率は、運用開始半年間に急にあがったという。
「最初、設備予約以外は一部の社員が積極的に使っているだけでした。その後、徐々に広がってはいたのですが、ある時急激に広まったようで、気がついた半年後にはほぼ全員が使っていました。サイボウズに登録されたスケジュールなどの信頼度が上がると加速度的に利用が広まったようです。境界線は感覚的に利用者が20〜30%を超えたくらいだと思います」(冨永氏)

情報システム部情報システム二課 辻村 寛之氏
導入効果 〜「サイボウズ Office」は情報のインフラ
同社で最初に効果があったのは会議室を予約する「設備予約」である。。
「会議をするには人と部屋を押さえなくてはいけません。しかし、これは時間も手間もかかり、精神的にもフラストレーションがたまることでした。それが、『設備予約』『スケジュール』を使うと、相手と連絡が取れなくても空き時間がわかるので、全員に確認しなくても一度の操作で人も部屋も確保できます。以前の電話とノートを使ったやり方とは、圧倒的な違いを感じました」(冨永氏)
その結果、体裁だけの業務ならやめてしまおうという雰囲気ができ、『サイボウズ Office』は業務改善のきっかけになった。
「それまで二人体制だった受付が、一人で十分になる。予定ボードが必要なくなる。目に見えて効果が出始めたので、パソコンを一人一台普及させる追い風にもなりました。今では『サイボウズ Office』は当社の情報インフラとなっています」(冨永氏)
活用方法 1「設備予約」 〜 利用のきっかけを作り、仕事が計画的に
「設備予約」は最初、会議室、応接室の管理から使われた。以前は総務部で管理していたために、部屋を予約するには電話をする必要があった。会議が重なるときは総務部内で調整をして、変更のあった場合は担当者に連絡しなおしていた。
それが「サイボウズ Office」では、会議を開きたい人が直接自分で部屋の利用状況を見て、空いているところに予約を入れられる。予約と同時に出席者を指定すれば、その社員のスケジュールにも会議の予定が入力されるので、会議に関連することはすべて一連の流れで設定できる。 仮に希望の部屋が先に予約されている場合でも、予約を入れたのが誰なのかを知ることもできる。そこで部屋を交換したいときは当時者間で交渉することになった。
「この影響で、仕事が計画的になりました。前日までに人や部屋を抑えておかないと何もできませんから。これは特に忙しい人に効果的で、自分のスケジュールを入れておかないと、誰かに勝手に予定を入れられてしまうので、スケジュールの利用にも結び付きました」(冨永氏)
今では定期的な会議なら半年先まで予約が入っている状態だ。当初管理していたのは、会議室、応接室だけだったが、最近は社有車、プロジェクタなどの備品もこの機能で管理している。
活用方法 2「スケジュール」 〜予定を詳細に書いて、月報に利用
以前は、自分の予定を手帳や PDA で管理し、予定ボードなどに書き込んでいた。部署によっては予定ボードが真っ黒になっていたこともあるという。また、役員のスケジュールについては、予定表をワープロソフトで作って配っていた。それが今では「サイボウズ Office」で管理されている。
「サイボウズ Office 6」になってから、スケジュールの中にコミュニケーション機能がついた。今まで E メールや電話で連絡をとっていた、調整やそのスケジュールに関する簡単な打ち合わせなど、そこで完結するようになった。
「情報が集まることによって効率的なことはもちろんですが、結果コミュニケーションも活発になってきていますね」(辻村氏)
また、一部の部署では、「サイボウズ Office」のスケジュールが月報作成に役立っているそうだ。
「前は自分の一ヶ月の活動をまとめるのが大変だったそうですが、今は『サイボウズ Office』に書いた情報を見ながらなので、月報も書きやすくなったとのことです。しかも形だけの報告書よりも、必要な情報が書いてある実のある報告書になったのではないかと思います」(冨永氏)
活用方法 3「掲示板」 〜関係する情報はその画面でやりとり
「掲示板」では管理本部主体の連絡で、献血や訃報、同社の情報がテレビ放送されるときの日時、内容などが掲載される。 そういう情報は以前、廊下の掲示板の貼り紙などで掲示されていた。「サイボウズ Office」導入後、紙ベースの連絡は減ってきており、現在はほとんどが掲示板で流され、紙ベースのものは絶対見ておかなくてはいけないものに限定されてきている。
紙の連絡網から「サイボウズ Office」に置き換わったことで、情報を発信する側の業務効率がよくなり、情報伝達の速度が上がるというふたつの大きな効果があった。
活用方法 4「アドレス帳」 〜PDA と同期を取って持ち歩く
「サイボウズ Office」の「アドレス帳」は、営業部の取引先のマスター住所録として活用している。社員が自分の情報を入力して、部全体で共有しているのだ。以前はエクセルのファイルで住所録を作って公開していたが、「アドレス帳」のほうが共有するには都合が良い。 そしてそのデータを「サイボウズ Office 6 シンク」の機能で、Palm やザウルスなどの PDA に移して持ち歩いている。「サイボウズ Office 6 シンク」は「サイボウズ Office 6」のデータを PDA に同期するためのオプションのツールだ。
「実は『サイボウズ Office 6 シンク』は会社で購入したものではなく、個人持ちなのです。PDA 自体が個人所有なのもありますが、サイボウズのホームページにはお試し版があるので、一度使ったら便利すぎてやめられないのでしょう(笑)」(冨永氏)
活用の工夫 〜会議室予約だけは強制的に始める
同社で「サイボウズ Office」がこれだけ活発に利用されているのは、設備予約を最初に始めたことが大きい。「サイボウズ Office」導入にあたって、ルールらしきものは定めていないのだが、会議室の予約だけは電話での予約をやめて、強制的に「サイボウズ Office」に移行した。
もともと会議室は、共有性が高い。その分、調整を担当していた総務はその業務だけでも時間が取られていた。それが、「サイボウズ Office」を使えば会議室の利用状況が見えるので、早めに担当者自身が予約するようになった。それに、会議室を予約すると、出席者のスケジュールにも予定が入る。その結果、誰かに入れられる前に自分の予定を書き込むようになり・・・と派生的にスケジュールも活用されるようになった。そうして、いつの間にか社員の間で「『サイボウズ Office』にある情報が優先される」という不文律が定着してきたそうだ。
「忙しい人ほど予定が楽に埋まっていきます。会議の相談を受けたときに『部屋を取っておいて』と頼むと自分のスケジュールにも入っているわけですから。仕事のうまい人ほど『サイボウズ Office』を上手に使っているといえるでしょう」(冨永氏)
これだけ活発に使われているのは、無制限ライセンスを購入したことも要因になっている。何かをやろうとしたときに、無制限ライセンスなら「料金が追加でかかるわけではないので、とりあえずやってみよう」という話になる。そして実行してみれば、やろうとしたことが実際に目で見ることができる。その結果、実行するスピードが早くなったそうだ。
「それほどパソコンの得意な社員が多いわけではないのですが、こちらの予想以上に使われていて『うちの社員もなかなかやるものだ』と思っています(笑)」(冨永氏)
今後の展望 〜「ワークフロー」を軸にポータル的な使い方を目指す
今後「サイボウズ Office」は同社のポータルとして活用していく計画だ。そのために現在は導入をしていない製造部門・研究所などの運用を徐々に始めている。
最近、導入した研究所では、導入直後から怒濤のように本社から会議の予定や連絡が飛んでくるようになったそうだ。逆にそれほど情報共有の必要が高くない製造部門ではテスト稼動の最中である。部門の中では好評ではあるが、工場で働く製造部門は他の部署と仕事の流れが異なるので、その部署にあった使い方や運用ルールを提案していくことを検討している。
最近導入したオプションの「ワークフロー」も同社の業務に深く関わってきている。「ワークフロー」は決まったルートに従って、申請書類を流すシステムで、同社では出欠勤の申請システムから利用を開始している。
「申請書類のデザインは今までの紙のフォームと同じにして、『使いやすいでしょう。もし問題があったら修正するから』と言って導入しました。これでうまくいけば、マスター登録やISO、クレーム処理、人事関係の諸届けにも利用するつもりです。人事部はかなり乗り気ですよ」(冨永氏)

システム概要
| ネットワーク | サーバーは本社内のWindows 2000 Serverを 1台で稼動している。接続回線は、各事業所は光ファイバーである Bフレッツ、本社はダークファイバー系が使われている。各拠点間は IP-VPN でセキュリティが確保されている。 |
|---|
システム概要図
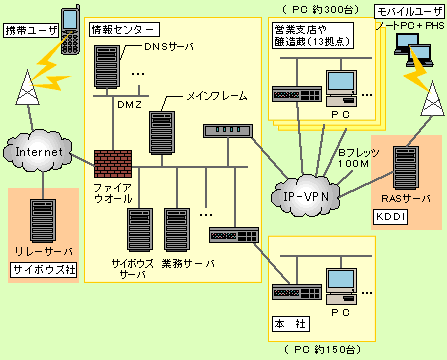
関連リンク
製品情報