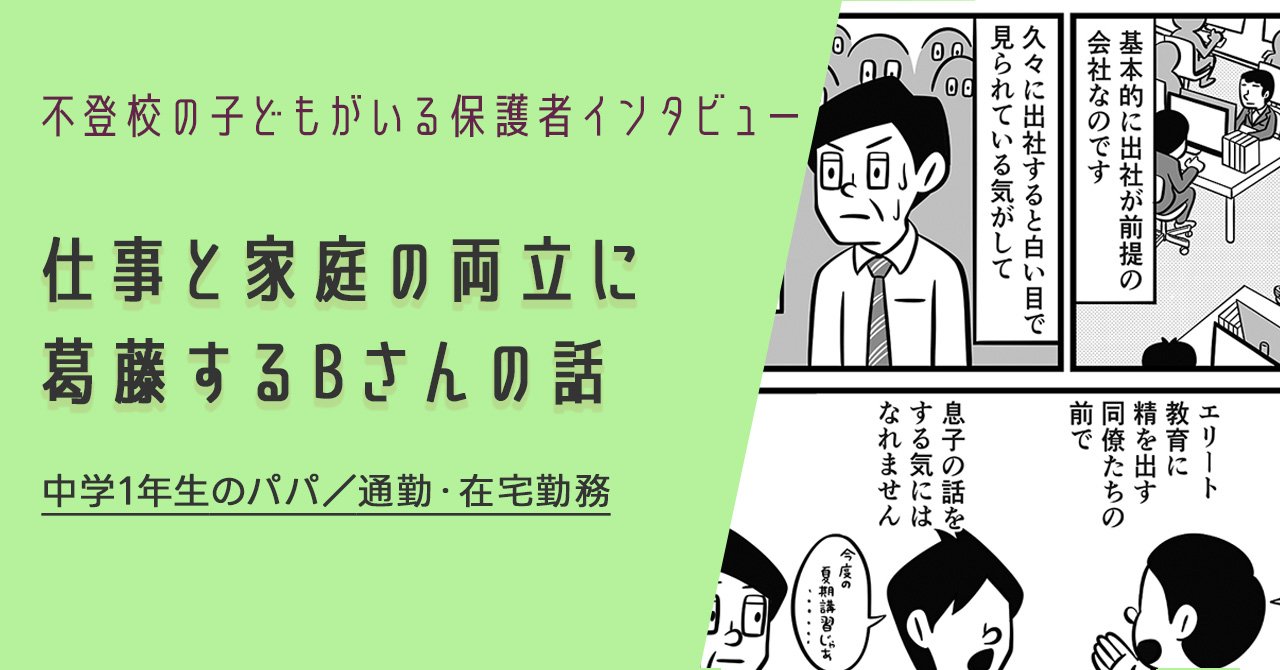サイボウズ ソーシャルデザインラボは、さまざまな価値観を持つ人々が安心して暮らせる社会を目指し、サイボウズ流のチームワークに基づいた社会実験(育苗実験)を行っています。2025年2月には、不登校・行き渋りの子どもがいる親を対象にインタビュー調査を実施しました。
お話いただいた具体的な不登校・行き渋りの時期のご経験について、ご本人たちの御了承をいただいた上で、経験談として掲載しています。全6本を順次UPしてまいります。
今回ご紹介するのは、都内在住の男性・Bさんのお話です。
中学1年生のお子さんは、学校に行ける時は行くものの、連続して数日休むこともあるなど登校頻度にムラが見られます。この状況で最も頭を悩ませているのが、仕事との両立と家族間の関係です。「もう(仕事を)辞めた方がいいんじゃないかと思うことがある」と話すBさんに、率直な思いを聞きました。
マンガで見る「仕事と家庭の両立に葛藤するパパのエピソード」






テキスト版エピソード
先生、同級生... 学校での人間関係が行き渋りのきっかけに
「最初に行かなかった原因は、提出物が出てなくて、みんなの前で先生から怒鳴られたことだったようです。その時は4〜5日くらい行かなかったですね。僕が担任の先生と話をして、やっと行けたような感じでした。今はクラスの中でちょっと結構乱暴な口調の子がいて、その子から嫌なことを言われたりして行けなくなった感じですかね。」
中学に入学してから行き渋りの傾向が見られていたBさんのお子さん。年末になってそれがさらに強くなり休むことが増えてきたと話します。
学校に行きたくない理由はすぐに言ってくれず、一緒に時間を過ごしている中でポツリポツリと話してくれるそうです。
「なんかこう...『今日頭が痛い』とかって言うんです。それで『頭痛いんだったら病院行かなきゃいけないんじゃない?』とか言うと『病院に行くほどじゃない。自分でわかるんだ』と。しょうがないから、僕は仕事を在宅に切り替えたり休んだりしています。お昼ご飯とか食べながらよくよく聞くと、『〇〇君に実はこう言われて......』ということを言い出す感じです。で、まぁ僕が学校に電話かけて先生に相談して。子供には『先生が注意してくれたから、次なんかあったら先生が頑張ってくれる』って言うとようやく行くみたいな。それでも2日ぐらいはかかりますけど。最近はそんな感じですね。」
不安定な登校状況 仕事の調整が負担に
学校に行ったり行かなかったりを繰り返すお子さんの状況になんとか合わせながら対応しているBさん。
学校に行けるよう働きかけてはいるものの、様子を見ていると「無理はさせられない」「一人にはできない」と感じるようです。
「どうしても朝は『(学校に)行け』って言っちゃいますよ。行きたくないのに無理に行かせても逆効果と分かってはいるんですけどね。メンタルだったりとか、学校でなんかこう嫌なことがあったりしたら、やっぱり一人にはさせられないなと思うから、僕が在宅に切り替えてそばに付き添うようにはしています。
子どもの自殺とかも最近増えているので心配なのですが、なかなかちょっとこの状況は困ったもんだなとは思いますよね。」
Bさんが最も頭を悩ませているのが、仕事との両立です。
Bさんが勤務する会社では在宅勤務が認められていますが、少数派であることは確か。どうしても周囲の目が気になってしまうと話します。
「僕は在宅もできるんですが、やっぱり会社で白い目で見られるし、立場がどんどんなくなっていく感じがします。妻は在宅ができないみたいなので、どうしても僕の負担が重くなってきますね。
それで『なんで俺にばかり負担がかかるんだ』と妻と言い争いになってしまうんです。その喧嘩でさらに子どもは『もう行きたくない』となってしまう。ものすごい悪循環っていうか、もう地獄ですよね。だったらもう(仕事を)辞めた方がいいんじゃないかと思うことがあります。
うちの子どもが不登校気味だというのは僕の上司には伝えてあって、上司は『お子さんのそばにいてあげてください』みたいな感じで言ってくれますけど、他の人(同僚)は知らないですから...。」
職場の理解がもっと得られればと思う一方で、不登校に関する話は周囲には打ち明けづらい複雑な胸中を話してくれました。
「(子どもの不登校は)同僚には言い出しにくいです。それは自分の子育てが恥ずかしいっていうことではなくて、なんかそれを言い訳にして仕事してないっていう風に見られそうな気がして。『うちだって介護してるのに』とか『まだ子供がいて、会社に行けたり行けなかったりすることがあるのに』っていう人もいるでしょうからね。
あと、同じように子どもがいる同僚との話でも、ちょっと話の立ち位置も違ったりするんですよね。『受験するならどういう塾がいい』とかね。今日、明日のことで悩んでいる僕からすると、『冗談じゃない、うちそんなレベルじゃ今ないし』と思ってしまう。だからとても話す気にならないというのもあるんですけどね。」
この子に合う居場所はどこなのか 模索が続く
学校を休む頻度が増えてきた今、将来的にどんな居場所を用意してあげたらいいのかについて考えることが増えてきたと言います。
「本人は今の学校から変わりたくないみたいなことは言ってるんですが、子どもにあった学校はどこなのかなって考えます。学校が合わないんだったら、あの子に合う場所を探した方がいいと思うし、そんなに簡単に見つからないから悩んでいます。」
今通っている学校にはなかなか相談しづらく、子どもの状況共有のみにとどまっていると言います。中学生ということもあり、進路の問題と併せて考え始めていると言います。
「短期的には、ストレスを感じないでやっぱり『楽しかった』って、学校から帰ってきてくれるのが一番の喜びなので、本当はね。今の学校を諦めて他に行くってなったら、もう今の学校は手助けしてくれないですから、もちろん自分たちで探さなきゃいけないんでしょうけど、それがやっぱり大変ですよね。だってどこの学校がいいのかなんてもうわかんないですし。
長期的にはやっぱり高校ですよね。学力も追いついていないし、高校受験はもう正直無理なんじゃないかって思います。多分このままだったら通信(通信制高校)だろうなぁとは思っていますけど。」
会社で打ち明けづらい家庭事情 多様な働き方が認められるようになってほしい
最後に、多様な働き方について寛容な社会になってほしいと切実な思いを語りました。
「在宅勤務ができなかったら、うちは破綻してます、確実に。実際、僕の友達でも子どもが不登校になって会社辞めた人いますもん。『仕方ないんだよね』みたいなことを言ってましたけど、辞めてしまうと経済的にもっと大変になっちゃいますしね...。
同じように不登校じゃなくて、例えば僕らの年代だと介護だったり子育てだたり、そういうことで仕事に制約がありながら働いてる人もたくさんいます。だからそういう人たちが働ける、多様な働き方に対する理解はもう必須だと思います。これから働き手がどんどん少なくなっていくわけですから。いろんな制約ある中でもキャリアアップしていける社会にならないと、安心して子育てできないですよね。」
不登校はもはや家庭や子どもだけの問題にとどまりません。
Bさんの言うように、不登校に限らず、仕事をしたい人が離職せざるを得ない状況に追い込まれないよう、働き方の柔軟性や職場で理解し合える環境を作っていくことが、社会で生きる私たち一人ひとりに求められます。
執筆担当

イラストレーター:山里將樹(やまざと・まさき)さん
2013年よりフリーランスのイラストレーターとして活動中。テレビ番組をはじめ、書籍、雑誌、Webメディアなど、さまざまな媒体でイラストを手がけています。
> 詳細はこちら