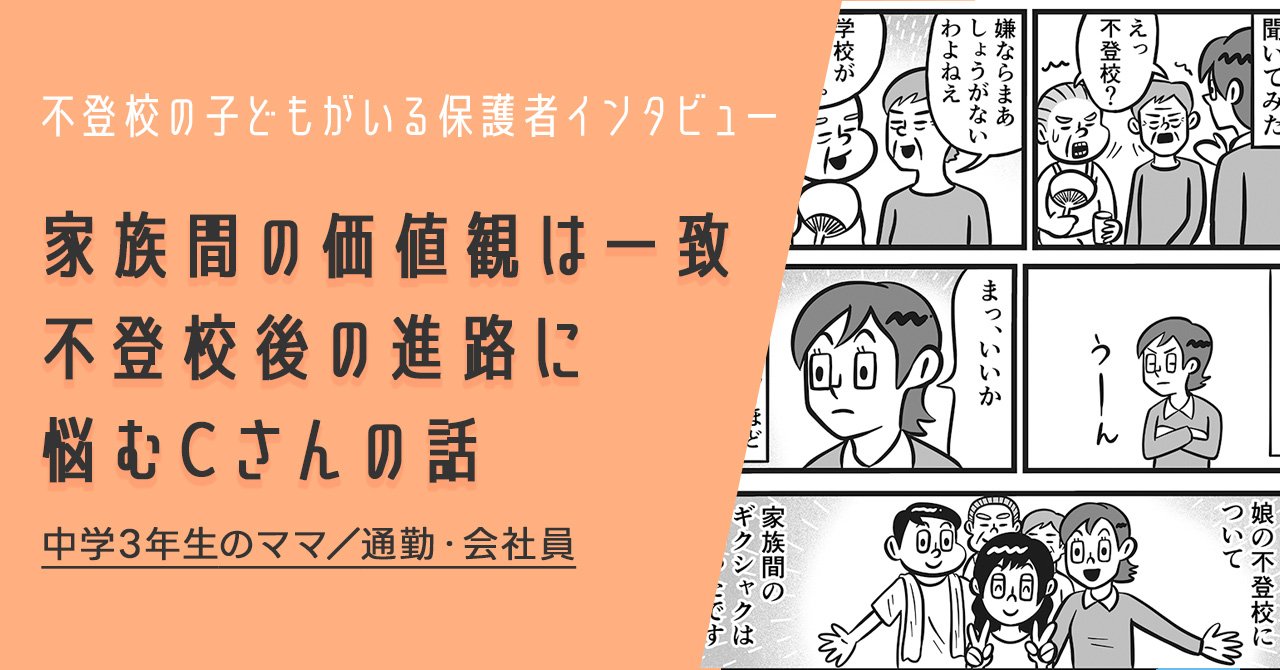サイボウズ ソーシャルデザインラボは、さまざまな価値観を持つ人々が安心して暮らせる社会を目指し、サイボウズ流のチームワークに基づいた社会実験(育苗実験)を行っています。
2025年2月には、不登校・行き渋りの子どもがいる保護者を対象にインタビュー調査を実施しました。
お話いただいた具体的な不登校・行き渋りの時期のご経験について、ご本人たちの御了承をいただいた上で、経験談として掲載しています。全6本を順次UPしてまいります。
今回ご紹介するのは、都内在住のCさんのお話です。
不登校になっている中学3年生のお子さんはフリースクールに通っています。「中学生の不登校は進路の問題と重なるので、不安な部分が大きかった」と話すCさん。居場所や進学に関する情報集めなど、苦労した点も多かったようです。
マンガで見る「家族間の価値観は一致。不登校後の進路に悩む母のエピソード」






テキスト版エピソード
理由は不明 体調不良を訴えることが多くなった中2のころ
中学2年生から学校に行かない傾向が出てきたCさんのお子さん。中学3年生になってから1ヶ月も経たないうちに、ほとんど通わないようになりました。
「中学2年生ぐらいから徐々に休むことが多くなりました。理由はいまもよくわかっていません。
最初は『体がだるい』とか『頭が痛い』とかで休みがちになり、仲の良いお友達が学校に行かない日は自分も行かないとか、そういった感じで始まりました。行ったら途中で帰ってくることもなく普通に過ごせるんですけど、行くまでに渋ってしまうっていう感じでしたね。学校はもともと好きではなさそうだったので、特に驚きはなかったんですけど......。」
「最初は『頭痛いから遅刻する』『休みはしない』っていう感じで言うんです。でも結局行かない、みたいな。なので、一応『行った方がいいんじゃない?』って声かけはしていたんですが、休みたいって言われた日は『分かった』って言って休ませていました。」
夫婦・家族間の価値観の一致が精神的な負担減に
理由が気になりつつも、なるべく子どもの気持ちを尊重することに努めてきたCさん。そうすることができたのは、家庭内での意見が一致していたからのようです。
「本人の状態を見ているとなんとなく......あまり行くと良くない感じがしていたので、無理に行かせることはしませんでした。
夫婦間の方針は『別に行きたくなかったら行かなくていいんじゃない?』という感じで合っていたし、両親(子どもにとっての祖父母)も『なんで行かないの?』とかは言いませんでした。なので、私自身は心配したし、行かないことに対してストレスが溜まっていた部分はあるけど、特別大きな心境の変化はなかったですね。」
お子さんの不登校について、夫婦間・家族間で大きな考え方の違いはなかったCさん一家。そのため対話や相談ができ、比較的落ち着いて対処できたと話します。
どうしても進路が心配 学校の先生のすすめでフリースクールへ
一方で、中学生ならではの悩みや難しさを感じた点も少なくなかったようです。
「やっぱり全く行かなくなった中学三年生の一学期ぐらいが一番辛かったかなと思います。どうしても進路が気になって、自分の精神的ダメージが一番大きかったです。『将来どうなっちゃうんだろう』『どんな大人になるんだろう』っていう心配が常にありました。
中学生になると保護者同士の付き合いもほとんどなかったので、話もなかなか聞けないんですよね。『みんなどうしてるんだろう』って調べてもあまり情報は出てこなかったです...。」
そうした中、お子さんが通う中学の先生に相談したところ、大きく状況が動きました。
「学校の担任の先生が親身に相談に乗ってくれる方で、フリースクールを紹介していただいたんです。
そのスクールは30分とか短い時間行っただけでも出席になるところ。子どもの状況的に比較的通いやすい上、学校とも連携しているので、テストもフリースクールで受けることができました。
中学3年生は受験があって、出席日数がどうしても関係してくるので、面談をした翌日から通うことにしました。たまに休むこともありましたが、過ごし方や通い方が自由なので本人にとってハードルは低く、外に出るきっかけになっていたと思います。」
「通信制高校に通いたい」 希望の進路が出てきた
フリースクールに通いながら過ごしていたCさんのお子さん。進路についてはお子さん本人から「通信制高校に通いたい」と希望があり進学を決めたと言います。
「子どもはダンスをやっていて、周りに通信制高校に通っている子が結構いるんです。年上の子が多いので、いろいろ聞いたり会ったりして情報を集め、本人から『今(学校に)通っていないから多分高校も通わない、通えない。通信制高校に行きたい』と希望を話してくれました。
通信制高校は、私にとってあまり身近でなかったので『なんでかな?』という気持ちも最初はあったのですが、いろいろ調べていくうちに安心感が出てきましたね。一緒に調べて、本人が行きたいところを探させました。
こうして本人が情報を集められたので、私自身はあんまり苦労はしなかったですが、進路については学校とかでもあまり紹介してもらえなかったので、親が一から調べないといけないってなると大変だと思いますね......。」
中学生の不登校となると、大きくのしかかってくる進路の悩み。
Cさんのご家庭のように親子・家族間で相談できる環境を作ること、幅広い進路の選択肢を知っておくことに加え、学校やフリースクールでも積極的な情報提供ができるようになると、最適な解決策や対応が見えやすくなるかもしれません。
卒業まであと少し 自ら友達と学校で過ごす選択を
不登校に関する支援についてあるといいなと感じるものを教えてもらいました。
「それぞれの子に合った支援みたいなのがあんまりないなって思うんですよね。その子、その子でなんだろう......性格とかも違うので、個々の違いやニーズに沿ったものがほとんどないなっていうのは感じました。
うちの子の場合、カウンセラーの方を紹介してもらっても、あまり気が進まず行かなかったんですけど、子どもの友達はカウンセリングが合って受けてたみたいです。話を聞いていただくのも大事なんですけど、もうちょっと違う部分でサポートとか支援とかをしてくれる取り組みがあるといいなと思いました。
あと、私たちのように学校からフリースクールに繋げてもらえるようになると、本当にありがたいなと思います。深く悩みを抱えている親もいれば、ちょっと不登校の傾向が出ていて『どうしよう』って悩んでる親もいるので、同じような悩みを持ってる人と話せる機会があると安心感があるかなとは思いました。」
Cさんはインタビューの最後、こんな感想を話してくださいました。
「これまで不登校に関する話ってできなかったんですよね。なので今、心がちょっとスッキリしました。こういう話せる場所がなかったので...ありがとうございます。」
不登校についてもっとカジュアルに話せる環境、相談ができる相手やコミュニティ作りも不登校のお子さんがいる保護者への支援に繋がるのかもしれません。
執筆担当

イラストレーター:山里將樹(やまざと・まさき)さん
2013年よりフリーランスのイラストレーターとして活動中。テレビ番組をはじめ、書籍、雑誌、Webメディアなど、さまざまな媒体でイラストを手がけています。
> 詳細はこちら