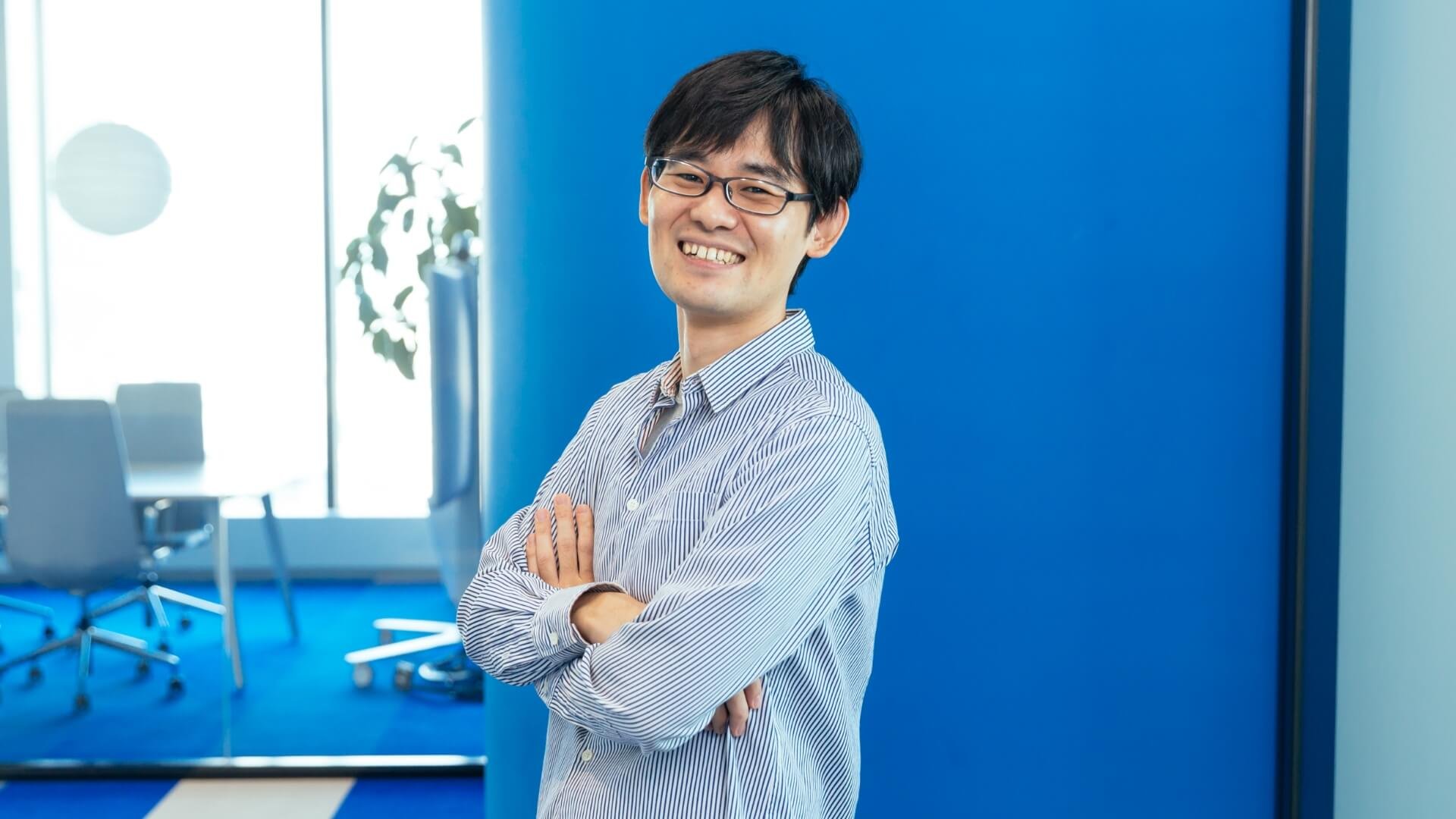プロフィール
佐藤 鉄平
開発本部長
2007年新卒入社。長年にわたりサイボウズでキャリアを積み、現在は開発本部の本部長を務める。パッケージソフトからクラウドサービスへの転換期を経験し、kintone(キントーン)などの主力プロダクトの成長を牽引してきた。XなどのSNSでは@teppeisとして、JavaScriptを中心にOSSや執筆活動にも取り組んでいる。
情報共有ツールの先駆けである「kintone」をはじめ、さまざまなプロダクトを展開するサイボウズ。時代の変化に合わせ、パッケージ製品の提供からクラウドサービス展開への移行、グローバル進出と進化を続けてきました。その変革を牽引しているのが開発本部です。AIへの挑戦、レガシー技術の刷新、グローバルへの対応など、これからのビジョンや開発組織の魅力について、また未来の開発チームに求められるスキルについて、本部長の佐藤に聞きました。
プロダクトとAIの融合により、新たな価値をユーザーへ
私がサイボウズへ入社した当時、従業員数はまだ200名ほどでした。18年の時が経ち、2025年は連結1,400人以上の会社になりました。当時は50〜70人ほどの規模だった開発本部も、海外拠点を含めて300名ほどの組織になっています。最も大きな変化は、プロダクトの性質です。当時はパッケージ製品として開発していたものが、今はクラウドサービスとして世界へ展開するようになったことです。ユーザー数も使われ方も当時とは大きく変わってきています。この変化に際して開発本部では、プロダクトの企画や開発にとどまらず、継続的な改善により製品を進化させていく戦略的な役割も担っています。
そんな私たちが、今後のテーマとして掲げるものには大きくふたつあります。
第一のテーマは「AI」への取り組みです。kintoneはエンジニアでない人でも自分の業務に必要なシステムを作れる・改善していける手軽さを重視しており、その特長にAIの性質は高い親和性を持つのです。指示に応じて回答したり、タスクを実行したりするAIの手軽さをどうプロダクトと融合させ、ユーザーに価値として届けていけるかが今の課題です。
「AIはエンジニアの職を脅かす」という声もありますが、サイボウズの開発チームはAIの台頭を非常に楽しんでいます。社内にはAIの専門家が集うチームもあり、プロダクトや部門を超えてAIに関する知見を蓄積しています。ツールの提供や共有イベントの開催など、それぞれが積極的にキャッチアップに取り組んでいるのです。またAIチームが窓口となり、AI活用のルール整備も行っています。セキュリティ部門や情報システム部門、法務部門と連携し、それぞれの視点から意見を出し合いルールを制定しています。AIの専門家が集うチームがAIを使ってやりたいことを吸い上げ、それを実現するための現実的な運用方法を考えていくのです。このように「やりたいことを阻害しないためのルール整備」が進んでいることも、積極的なAI活用へのチャレンジを後押ししているといえるでしょう。

「部門導入」から「全社導入」、そしてグローバルへ
第二のテーマは「エンタープライズ領域へのチャレンジ」です。特に主要プロダクトkintoneをより成長・拡大させることを目指しています。現状、kintoneは日本国内で38,000社の企業に導入されていますが、その多くが「部門導入」の段階にとどまっています。この導入数を拡大し、「全社導入」に到達させるための機能開発や改善に取り組んでいるのです。
このチャレンジを支えるのが、「自社製品の世界一のヘビーユーザー」を自負するサイボウズの姿勢です。社内では業務上必要だと思うアプリがあれば、誰でもすぐにkintoneで作り、活用し、改善していく風土が根付いています。「必要とする人が、必要な機能を持ったアプリを作れる環境」を実現していくために、誰もが常に自分事として課題解決の方法を考えているのです。
このように全社員が自由にその機能を使えてこそ、情報共有のサービスは真価を発揮します。そして導入規模が拡大する過程で、性能に関する課題も新たに発生するでしょう。企業の規模によりガバナンス・セキュリティ要件などの解決も不可欠になります。グローバルへの対応もその一つです。
サイボウズでは2025年時点で、kintoneをよりグローバルに展開していく戦略を進めており、どの機能も「世界で使われること」を意識した開発を行っています。この最適化を進める中で、ボトルネックになるのはレガシー的な仕組みです。kintoneがリリースされた15年前当時の機能は古く、今の標準的な機能との連携が難しいことが多々あります。既存の仕組みをブラッシュアップして今の標準に合わせていくことも、非常に重要な取り組みのひとつなのです。国際化への対応は多くの企業が行っていますが、実際に海外で使われているプロダクトに携われる機会はそう多くありません。グローバル展開ならではの思考や開発手法に触れることで、開発者として幅広い経験を積めるでしょう。

技術と誠実に向き合える環境でエンジニアとして成長
開発本部ではチームで議論して物事を進めていくということが日常的に行われるため、コミュニケーションスキルやチームワークは非常に磨かれます。エンジニアは個人のスキルと知見でコツコツできる仕事というイメージもありますが、サイボウズで求められるのはそのスキルだけではありません。これからのエンジニアには、「決められた仕事をこなす対応力」ではなく、「オーナーシップを持ち、プロダクトの成長をけん引する開発」が求められます。誰もが使いやすいツールを生み出すために、常に議論を重ねながらチーム開発を進めるサイボウズなら、そのオーナーシップも自ずと養われていくでしょう。
kintoneのような歴史の長いサービスを提供するサイボウズですが、先に挙げたグローバル対応などの改修のほかに新サービスの立ち上げも活発に行われています。だからこそ、「既存の大規模プロダクトの安定化・効率化」が得意な人も、「ゼロイチで新規プロダクトを生み出す」が得意な人も活躍できるのです。社内ではレガシー技術の解消に向けた取り組みも進んでおり、会社として今後もしっかり投資をしていきます。
こういったチャレンジを叶えていくために、サイボウズでは課題やユーザー、仲間と真摯に向き合い、意欲的に技術に挑戦できる環境を整えています。その結果として「オーナーシップを持ち開発に取り組めるエンジニア」が育っていくのです。極端に言えば、大枠の戦略が決まってしまえばプロダクトマネージャーがいなくても進められるくらいのチームになることが理想です。そしてそこに必要なのは、長年の経験に裏打ちされたスキルだけではありません。「こうすればよりプロダクトがよくなるだろう」「こんなユーザーの悩みを解決したい」と考え抜く姿勢も非常に重要です。実際に、新卒入社の社員もチャレンジングな姿勢やユーザー視点を活かした意見を発信し、活躍しています。
自身が関わるプロダクトが、社会に価値を提供していると実感できること。そして変化の激しさの中でも揺るがない「ユーザーや技術に誠実に向き合う姿勢」が、私たちのチャレンジを常に後押しします。プロダクトを通じて、社会をより良くする。こうした価値観に共感できる方を、サイボウズではお待ちしています。